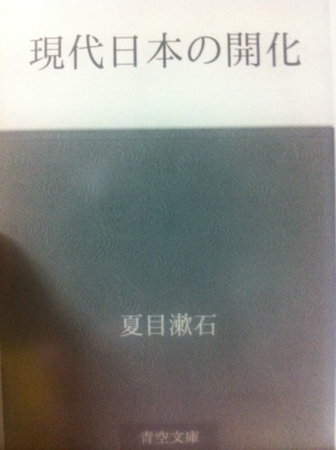
これもまた講演テキストで、明治44年8月に和歌山で行なわれたもの。ネット上でも読めます。
完全にひとりバガヴァッド・ギーター状態の漱石グルジでありますが、今回は最後のほうに恐るべき予言的指摘があり、思わずのけぞった勢いでブリッジしてしまいそうでした。
だって、こ、これ……
とにかく私の解剖した事が本当のところだとすれば我々は日本の将来というものについてどうしても悲観したくなるのであります。外国人に対して乃公おれの国には富士山があるというような馬鹿は今日はあまり云わないようだが、戦争以後一等国になったんだという高慢な声は随所に聞くようである。
おれの国には富士山があるというような馬鹿ぁぁぁああああああ”あ”あ”あ”〜。
そして今回も「つかみ」がしびれる。そんなに長くもないと思う前置きの後に。
さっき牧君の紹介があったように夏目君の講演はその文章のごとく時とすると門口から玄関へ行くまでにうんざりする事があるそうで誠に御気の毒の話だが、なるほどやってみるとその通り、これでようやく玄関まで着きましたから思いきって本当の定義に移りましょう。
こういうの大事ね〜。すてき。わたしも太陽礼拝ABが終わった頃に「はい、やっと玄関までたどり着きました☆」って、パクッちゃお。
今回はプルシャ、プラクリティ、ドーシャの話が多いです。わりとサーンキヤ寄りです。
元来人間の命とか生とか称するものは解釈次第でいろいろな意味にもなりまたむずかしくもなりますが要するに前申したごとく活力の示現とか進行とか持続とか評するよりほかに致し方のない者である以上、この活力が外界の刺戟に対してどう反応するかという点を細かに観察すればそれで吾人人類の生活状態もほぼ了解ができるような訳で、その生活状態の多人数の集合して過去から今日に及んだものがいわゆる開化にほかならないのは今さら申上げるまでもありますまい。
「この活力が外界の刺戟に対してどう反応するかという点を細かに観察」の「活力」をプルシャに置き換えればそのまんまサーンキヤであり、「開化」はカルマ。
ただし、刺激そのものに定義を乗せていくのは漱石流!
この二様の精神すなわち義務の刺戟に対する反応としての消極的な活力節約とまた道楽の刺戟に対する反応としての積極的な活力消耗とが互に並び進んで、コンガラカッて変化して行って、この複雑極まりなき開化と云うものができるのだと私は考えています。
「義務の刺戟に対する反応としての消極的な活力節約」「道楽の刺戟に対する反応としての積極的な活力消耗」。前者がタマスで後者がラジャスなんだけど、「義務の刺激」「道楽の刺激」と定義するところが、インド人より進んでる!
この講座には、「余剰エネルギー」の話も出てくる。
好んで身体を使って疲労を求める。吾々が毎日やる散歩という贅沢も要するにこの活力消耗の部類に属する積極的な命の取扱方の一部分なのであります。
中村天風さんより先に日本でこれ唱えてたのねグルジ! こりゃ大発見。
で、このあと、行きたいときじゃなくても行かなければいけないときが出てくるから、動かないで用を足そうとする工夫が発生するとしていて、(以下、その後の続き)
となると勢い訪問が郵便になり、郵便が電報になり、その電報がまた電話になる理窟です。つまるところは人間生存上の必要上何か仕事をしなければならないのを、なろう事ならしないで用を足してそうして満足に生きていたいというわがままな了簡、と申しましょうかまたはそうそう身を粉にしてまで働いて生きているんじゃ割に合わない、馬鹿にするない冗談じょうだんじゃねえという発憤の結果が怪物のように辣腕な器械力と豹変したのだと見れば差支さしつかえないでしょう。
そして電報が電話になり、電話がメールになり、メールがLINEになり……怪物のように辣腕な器械力。
わたしは、メールまでは後者の「身を粉にしてまで働いて生きているんじゃ割に合わない」が背景にあったと思うけど、LINEは完全に「なろう事ならしないで用を足してそうして満足に生きていたい」が背景にあると思います。
西洋で百年かかってようやく今日に発展した開化を日本人が十年に年期をつづめて、しかも空虚の譏(そしり)を免かれるように、誰が見ても内発的であると認めるような推移をやろうとすればこれまた由々しき結果に陥るのであります。百年の経験を十年で上滑りもせずやりとげようとするならば年限が十分一に縮まるだけわが活力は十倍に増さなければならんのは算術の初歩を心得たものさえ容易たやすく首肯するところである。
わたしは「誰が見ても内発的であると認めるような推移」のところを読み取れていないのですが、これは世が平等であるかのようなフリをして実はとんでもない労力の使い方をしているとか、そういうことかな。だとすると、これも予言に見えます。
今回のテキストは正直怖いくらい、グサグサきました。
「なんかとりあえず焦ってる」という状態で思考停止しがちなんですよね。個人レベルでも「あるわ〜」と思う。歴史を学んでいると思うけど、ヨーガ・スートラが日本で言う古墳時代の真ん中ごろだと思うと、かなり学問も素地の違いを感じます。
海外に出たときはせめて「まぁ言うても昨日今日の国ですから」くらいの気持ちでいよう。そして卑屈になることなく、「わてらヨーガ・スートラの頃にハニワこしらえてましたけど、あなたたちがいま熱狂しているそのドラえもんは、わてらの国の人のおもろい人が考えたもんですぜ」と、そういうちょっと持ち直せる材料があればいい。
おおげさなことって、やっぱりねじれてるよね。

