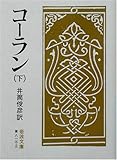この本のまえに井筒氏の「コーラン」を読んだのですが、マホメット(ムハンマド)の人物史と併せ読むことで、史実の書としてのコーランの側面が理解しやすくなりました。「コーラン」は上中下巻の3冊にわたるボリュームなので、とっかかりとしては「マホメット」のほうが入りやすいかもしれません(この本はコーランの十分の一以下のボリュームです)。
アッラーとムハンマドの関係のおもしろさはなかなか端的にお伝えしにくいものがあるのだけど、かねてよりの「アッラーがなんだかオッサンすぎる件」という疑問が、この本で解けた。
どんな内容かというと、牧野信也氏の解説のとおりで
本書は『マホメット』という書名ではありながら、さらに広く、イスラームという宗教はそもそもどのような状況の中から誕生して来たか、を知るための絶好の手引きでもある、と言えよう。世にマホメット伝多しといえども、本書のようにジャーヒリーヤ時代についての徹底的考察から説き起している例を他に私は知らない。
イスラーム以前の「無道時代」の解説にしっかりボリュームが割かれているのがよい。
この後の引用に出てくる「ベドウィン」というのはアラブ系遊牧民のことなのですが、イスラームが起こる以前の精神的価値観は、それはそれでなかなかすばらしい、清貧かつ高貴な志。著者も『ともすれば「底抜けのお人好し」』と表現しています。その、ベドウィン的騎士道精神の解説のあとに、以下の説明が続きます。
<34ページ 砂漠の騎士道 より>
しかしベドウィンたちが、こういう徹底的な人情味を見せるのは、ただ自分の部族の中にいる時だけに限られていた。同じ血を分けた家族、同部族民、友人、客人に対してはどこまで情が厚いかわからない彼らなのに、一旦部族の圏内を踏出して、異部族に向うやいなや恐るべき悪鬼に変貌してしまうのだ。
「ただ自分の部族の中にいる時だけに限られていた」というところは、中国人の感覚と少し似たところがある。ただ「圏外」への対応は、激しい、もっと別のもの。イスラームではこの時代を「無道時代」というのだけど、イスラームをきっかけに、他の国や宗教との歩みの違いにあらためて気づくことがとても多い。
<41ページ 砂漠の騎士道 より>
無道時代のアラビア人には霊魂に関して幾つもの考え方があり、魂はいかなるものかという問題について種々なる意見が対立していた。たとえば、その中の或る一派の主張するところによると、霊魂とは血液であり、精神は身体の内部に在る空気に過ぎず、それが気息となって出るのであると。また他の一派に従えば、霊魂は鳥であって、人が死んだとき、あるいは殺されたときこの鳥は身体から外へ飛んで出る。そしていつまでも死者の墓辺に出没し、その死を悼んで止まぬ、と。
コーランに「鳥占いに出てる」という話(章句)があるのですが、この「霊魂に関する考え方」は独特で、すごく面白い。インドとアラブの間にイランがある地理や、ゾロアスター教の存在を含めて、この流れは興味深い。
マホメットは、使徒(メッセンジャー)です。コーランを読むとその様子がもっとイメージしやすいのですが、「ものすごく降りて来られちゃうイタコ」を想像すると、さらに理解しやすくなります。まずはここのエピソードから。
<88ページ 預言者召命 より>
マホメットが、自分は神の使徒であるという確固不動の自信に達するには相当の時間が必要だった。最初の体験のときも彼ははげしい恐怖と驚愕にとらわれて真青になった。
(中略)
気の弱い彼はその後もしばらくの間は、そういう体験があるたびに全身悪寒でがたがた顫えながら妻のところへ駆け込んで来るのだった。何遍か自殺しようとしたこともあった。しかし冷静で大胆な妻ハディージァは、これが悪霊の仕業ではなく、真に神の霊感であることを疑わなかった。誰よりも先に彼女が入信した。
妻とマホメットのエピソードも必読(25歳のマホメットに、40歳の妻)なので、気になる人は読みましょう。(この際そういうとっかかりでも、いいと思うの)
イスラームは、「使途が伝えた」宗教。このおもしろさとマホメットの人物伝は切り離せない。
<79ページ 預言者召命 より>
両親の温かい愛に包まれた懐しい幼年時代というものが彼にはなかった。成人してから、自分の子供の頃を憶い出すとき、彼の記憶に先ず浮んで来るのは苛酷な人生の試練ばかりだった。さればこそコーランの中には繰り返し繰り返し yatim 「親なし子」が重要なテーマとして現われて来るのだ。マホメットは悲しいにつけ嬉しいにつけ自分が孤児として育ったことを忘れることができない。
コーランには、「孤児」や「妻・女」に対する接し方の章句が多く登場します。その時点で「アッラーって、オッサンだよね」という印象を持たざるを得ないのだけど、マホメットの人生を追うと、なるほどなぁ、ということになる。「オッサンをマネジメントしながらオッサンに啓示してるから、結果オッサンぽくなっている」のか、と。
でね、このオッサンは、孤児だったの。25歳のときに現れたお金持ちの年上の妻が、はじめの信者になってくれたのよ。なんてことを踏まえて読むと、コーランは泣ける書物。特に親や家族に対する想いの記述は、少ないけれどズシンと響きます。
わたしはこの本を読んで、その後ダンテの「神曲」について調べてみるまで、「神曲」がイスラム圏で禁書扱いになっていることを知りませんでした。「神曲」は13〜14世紀のイタリアの叙事詩なんだけど、よくこんなこと書いたなぁと思う。(Wikipediaの「宗教的評価」に簡潔な記述があります)
そのうえで。
<16ページ 序 より>
もっともマホメットは三位一体を神とイエスと聖母マリアによって構成されているものと誤解していたのだから今日から見ると話はいささか可笑しくなるが、三位一体を構成するものが何であっても、いずれにせよ唯一なるべき神の内に三という数を持ち込むことは彼には我慢ができなかった。こうしてキリスト教とイスラームとは、そもそもの発端から不倶戴天の仇敵となった。しかもこの敵対関係が時とともにますます緊迫の度を加えて行ったことは言うまでもない。
このあと、ダンテの神曲の世界観がこの歴史背景とともに何を言いたいものであったのかの説明が展開されます。
<19ページ 序 より>
ダンテがこんな残虐な(というよりはむしろ不潔な)描写をあえてしないではいられなかった気持もよくわかる。無理もない。考えれば考えるほど腹が立って仕方がなかったのに違いないのだ。しかしこれでは学問にはならぬ。
この本は、マホメットがもたらした混乱とその背景をひたすら追って行く。それにしても、「しかしこれでは学問にはならぬ。」というテンポの軽快さ。シビれます。
コーランはマホメッドの活動拠点移動を機に、メッカ時代(前期)とメディナ時代(後期)の2期にわけて解説されることが多い。この前後期の説明が、「コーラン」ベースではなく「マホメットの人物史」ベースで語られるのが、この本の最大の読みどころ。
<64ページ マホメットの出現 より>
メッカ時代のコーランの章句を根本的に色づけていつものは神とその審判とに対する深い懼れの情である。「主の御前に顫えおののく者こそ真の信者なれ」とそこには定義されている。つまり信仰と恐怖とはほとんど同義語なのだ。ここでは恐怖とは人を一時的に襲ってはいつしか消えるかりそめの情緒ではない。またそれは何物かによって拭掃されるべき単なる気分でもない。むしろ人間存在の根源そのものが恐怖なのである。胸に恐怖なき人は人たるに値しないのだ。
イスラームを「性弱説のうえにあるもの」ととらえるとき、ここにひっかかりを感じる人は、仏陀の教えを経てからきたほうがよい。というような構図が成り立つところが、仏教とイスラームをあわせて学ぶことの醍醐味。
そして、このあと「預言者召命」の章で
後期になるとマホメットは盛んに旧約聖書を活用し出すので、人間創造もこんな生々しさをなくして創世記的になる。(86ページより)
と。これは、イスラームとキリスト教、ユダヤ教をあわせて学ぶことの醍醐味になるのだろうな。ここはまだ、わたしにはわからない。
「メディナの預言者」の章では、メッカから移動したメディナという地の宗教背景とともに、マホメットの人物像が語られます。以下すべて「メディナの預言者」の章より。
<102ページより>
元来このメディナという町は非常にユダヤ色の濃厚なところで、市の内外には古くから沢山ユダヤ人が住んでおり、一般に住民はヘブライ的な人格的唯一神の崇拝を見慣れていた。そればかりでなく附近にはまたキリスト教を奉ずる強力なアラビア部族も幾つか居住していた。従って、メッカとは違ってここでは啓示とか聖典とかいう考えが少しも奇異な感じを惹き起こさなかったのである。
(中略)
コーランのおもしろさは、イタコから戦術家へ変貌を遂げていくマホメットの20年史という側面もある。
<104ページより>
メディナへ移って来てから、マホメットの発表する「啓示」の性質がにわかに大きく転換し始めることは言うまでもない。今までのような暗い終末観やペシミズムでどうして地上の大帝国が建設できよう。メッカ時代の説教の魅惑的な特徴をなしていた終末観的表象は次第々々に遠のいて、啓示の内容は著しく現世的となり、かつての激しい抒情的な調子はかげをひそめて冗漫な散文調になる。現世的どころか、時とすると天啓がマホメットの私生活のしかも日常茶飯事の末葉にまで長々と干渉するのだ。
この「マホメットの私生活へのアッラーの干渉」によって、コーランは「とんでもなくためになる説教集」という側面を持つ。わたしが別名をつけるなら、「アッラーのマネジメント日記」。マホメット級の「バッシング耐性」をつけたい人に、コーラン以上の自己啓発本はないと思います。この点では世界最強かと。「罪悪感耐性」にバガヴァッド・ギーター、「バッシング耐性」にコーラン。ボヤキたくなったら「歎異抄」。この3冊があれば、たいがいのことは乗り切れるでしょう。
<105ページより>
メッカではコーランは「警告(タズキラ)」だった。メディナではそれはもっと肯定的な「導き(フダン)」(hudan)となった。かつてはあれほど深いペシミズムをもって現世の儚さを強調していた彼はもはや決して現世の悪口を口にしなくなってしまった。現世の悪どころではない、その現世の地盤の上に、今や祭政一致の大国家を建設しようという野心的な政治家の彼ではないか。この崇高な目的への進路を阻む者があれば、遠慮なく剣で切り殺してしまえ! かくてこの頃の啓示は信徒に向って盛んに戦闘を勧め出す。世にいわゆる「聖戦(ジハード)」(jihad)である。
イスラームを理解するとき、戦術家に成長していくマホメットの心の過程や背景を知らないと、まるで「信長のことば」のような理解になってしまう。あんなに弱気だったマホメットがここまでになっていく背景は、大河ドラマで見たい級です(ありえないけど)。
<109ページより>
マホメットは始めユダヤ人に大きな希望をよせていた。ユダヤ民族というものが、その信仰においてどれほど粘り強い ── いや執念深いと言った方がよさそうだ ── ものかを一向に知らぬ未経験で淳朴な彼は、彼のもたらす新しい啓示をも彼らはよろこんで受け容れるだろうと思っていた、これこそかつてアブラハム及びモーセに啓示されたイスラエルの神の言葉の継続として。しかしこれではあまりにお人好しすぎる。いかに苛酷な拷問を受けても、どんな惨烈な禍難の裡に投げこまれても絶対に父祖の信仰を守り通そうとするユダヤ人の宗教性はマホメットが考えていたような甘いものではない。
「甘いものではない加減」は深いところなので、学びたい人は、買って読んでください。
イスラームは啓示宗教なのだけど、「ちょっといい話」だけを切り出すことには、ちょっとためらう。その教えの中にはすごく沁みるものがたくさんあって、ときにマホメット個人の生きざまと結びついていたりする。
人間は、「自分は悪くない」「自分は助かりたい」と思いたい弱い生き物なんだってことを、イスラームの教えに気づかされる。「そんな弱いぼくらで、どうやって世の中を創っていくか」という希望の教えでもある。
性強説からの博愛、友愛よりもずっと強い底力を感じずにはいられないイスラーム。根はちょっぴり弱気でかわいかったマホメット。このギャップとコントラストがたまりません。