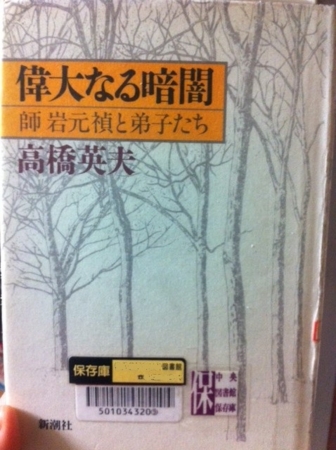
「三四郎」の広田先生のモデル説がある人物(岩元禎)を追ってみた、という本。ふたりとも「一高(現在の東京大学教養学部)」の教師で、漱石は英語、岩元禎はドイツ語の教師をしていたのだそう。有名な人の名前がたくさん出てくるけど、岩元禎は西田幾太郎と同級生で、弟子に九鬼周造がおり、高校時代の志賀直哉の家庭教師をしていたりする。
読んでみたわたしの想像では、「鼻から哲学の煙」「生涯独身」などのキャラクターのアウトラインは岩元禎のエッセンスを多分に盛り込みつつ、中身は漱石で、モーレツに面白いセリフは粟野健次郎の要素が強いのではないか、と感じた。粟野健次郎という人は面白さのレベルがとんでもないので後日に感想を分けます。
著者さんも
「偉大なる暗闇」は岩元禎とはほとんど関係がなかったといっていいだろう。広田萇のくろぐろとした内面の謎は、作者漱石自身が内部にかかえていた鬱々たる思いのほうに近かった、というのが正しい見方だと思う。
(中略)
しかし皮肉にもここで広田先生という類型に魂が吹きこまれ、人物が動き出すのだ。漱石の内面が人物の中に封じ込めてあったために、読者である若い人びとには広田先生が広田先生のままで静止してはいず、いつのまにか作中人物からはみだして動き出し、岩元禎という神話作用に達してしまったのであろう。(31ページ)
という。広田先生のキャラクターは、謎があってかっこよいのよねぇ。
岩元禎は漱石も多分に影響を受けたケーベル博士の影響下でギリシャ古典を読みこなした人だそうで、同級生の西田幾太郎がケーベル博士について書いている文章に登場しています。
ケーベルさんは始めて日本へ来て、日本の学生が古典語を知らないで哲学を学ぶと云ふことが、如何にも浅薄に感ぜられたらしい。私が或日先生を訪問してアウグスチヌスの近代語訳がないかとお聞きした所、先生はお前はなぜ古典語を学ばないかと云はれた。私は日本人として古典語を学ぶのは中々困難であると申上げると、それでもお前と同クラスの岩元君はギリシア語を読むではないかとのことであった。You must read Latin at least と云はれた。(36ページ)
もんのすごい勉強家だったようなのです。
で、わたしがなんでこの人にこんなに興味がわいているかというと、ドイセンの原著の講義をしていたらしいのです。ドイセンと岩元禎の関係を、この本の引用で紹介すると
ドイツの哲学者パウル・ドイセン(1845-1919)はショーペンハウアーの後継者で、インド哲学の研究で知られ、ベルリンとキールの大学で講壇に立っていた。(103ページ)
(中略)
ドイセンの原著はたしかに整然とした構成をとっていた。前編で形而下学(フィジーク)を扱ったのち、後編で形而上学(メタフィジーク)の体系に入り、認識論、自然哲学、美学、倫理学の順に章節を細分して哲学の基礎的範疇や概念を解説している。インド哲学の大家らしく、宇宙を論ずるときも霊魂不滅を説くときも、つねにヴェーダ文学や『マハーバーラタ』から引用している。ドイセン自らはプラトン主義者と称していたにもかかわらず、である。この点からも、岩本禎の「古典」世界とはかなり雰囲気の相違があった。しかし岩元禎は早くからドイセンを咀嚼して身につけており、哲学を志す弟子にはドイセンを推奨していたという事実がある。(105ページ)
(中略)
そのいかにもショーペンハウアー風な一節を岩元禎がどう表現(翻訳)したかを、「神と宇宙」(「哲学概説」の)という章から引用しよう。
意志の他には何者もあるなし、その正しき態度は否定なり、意志の昏乱は肯定なり、その現象と之が浄化作用は即この全宇宙なり。(106ページ)
わたしは夏目漱石の小説を読んでいると、なんでこんなにインド哲学っぽいのか不思議でしょうがなかったのですが、この時代のケーベル門下生の人びとの学問はここまですごかったのだなというのがわかって、目がギラギラしてしまいました。西洋哲学の視点で読んでいる人から見ると同じ記述でも「カントです」ということになるようなのですが、漱石の同僚にこんな人がいたというだけでもワクワクする。
ここから、いくつかのテーマに沿って感想を書いていきます。かねてより夏目漱石の小説の世界で気になっていたことです。
■当時の「友情」のアツさ
「吾輩は猫である」や「三四郎」「こころ」を読むと、とにかく男ばかりでツルんで気持ち悪いくらいなのだけど、そういう時代だったみたい。
少くとも明治の人間は友情の中で生き、友情に悩んでいた。夏目漱石は学生時代から正岡子規をはじめさまざまな友人との友情空間に生きていたし、『グレイグ先生』『ケーベル先生』といった小品文で、彼らとの人間的な結びつきを描いた。何よりも『三四郎』によって、広田先生という「偉大なる暗闇」を造型し、こういう友情空間が時代の胎動を帯びていることを証明した。さらに『三四郎』以後、『それから』『門』『こころ』『行人』といった小説によって、友人との関係に陰翳として必ずつき纏う背信や疑惑をくりかえし追いかけ、ほとんど絶望的な所にまで自分を導いていった。ホモ・アミクスの危機を先取りしたのが漱石であったと言えるだろう。(204ページ)
岩元禎という人も、とんでもなく研究ばかりしているのかと思いきや、友情にアツかったらしい。
岩元禎は当時としても異常に友情に対して固執し、相手の感情におかまいなく友情を振舞う特例的な人間であった。けれども相対としてみたとき、当時は今日とは比較にならないくらい、友情が生きていた時代であり、他人への熱い関与は美徳であった。その時代的雰囲気の中では、志賀直哉のように人間関係に癇癖のつよい人物でさえも、過剰な友情を押付けてくる岩元禎に、一旦は時代の美徳を典型的にあらわした人間を感じて敬意を払ったのである。
(中略・以後は志賀直哉の文章『ヴィーナスの割目』より)
岩元さんは一見、頑固一徹な人のやうに思はれてゐたが、それから暫くして、一高の同僚で山川信次郎といふ英語の先生が女の事で新聞種となり、学校をやめねばならなくなつた時、岩元さんは心から同情を寄せ、心配してゐた。山川さんは尺八がうまく、三曲の合奏などで、女の人の交渉が多く、つい、さういふ誘惑に陥る機会があるのだと同情してゐた。さういふ事には全く縁遠さうな岩元さんのこの同情振りは、わたしには何となくいい感じがした。
当時のアカデミック・ホモソーシャルのなかでも志賀直哉はわりと冷めていたらしい。でありながらのこの文章は、ちょっと微妙でおもしろい。そして漱石もできるだけ小説の中では引いた目線を心がけているものの、実生活はアツかったんだろうなと思う。普通に生徒も家に招き入れているし。わたしはインターネット上でイチャつくおじさんたちのホモソーシャルがいつもきもちわるくてしょうがないのですが、「あー、昔からなのねー」と思いました。
■ケーベル先生
ケーベル先生については漱石のテキストを読んでいたけれど、この本を読んだらより人物像が見えてきた。
ケーベルの友情空間の中で第一に名をあげるべき久保勉は、印象的な思い出をたくさん書いている。それらを集めた『ケーベル先生とともに』から二ヶ所引用してみよう。
私が何かの機会に、先生が頭に思い描いている理想的生活について尋ねた時、先生はかう答へられた、『大思想家の中ではカントとデカルト(その出征を除いて)の生活が私の理想にいちばん近い。スピノーザの生活ではない。私は彼のように孤独なのも又憎悪されて生きるのも厭だ。私は極めて簡素な生活をしたい。が、ある種の交際は好きだ。それに家庭も。ただ召使はあまり大勢ゐてはいけないし又性的関係をもつた婦人と一緒に住むことも。母親か、または従姉妹とか、又は伯母とかと一緒に暮すのは一番好きだ。君とも亦非常によく暮せる。』(128ページ)
なんかわかるなぁ。性的関係をもつた婦人と一緒に住むのが厭なところが。
■当時の師弟関係
昔は今と違って本がふんだんにあるわけではなかったので(そのあと岩波文庫ができる)、先生に直接ついて話を聞かなければならない時代だったそうです。そんななか、この本では当時聖者とまでいわれた三谷隆正という人(法学者)が書いた岩元禎の関係を追い、三谷隆正による追悼文を引用しつつ、以下の分析がされています。(興味深い内容です)
師の人格と言説をどこまでも一つのものとして理解しようとするとき、師の存在はその中に矛盾や弱点をかかえこんだ総体になるだろう。矛盾や背馳は師という総体の内部に吸収され、人間化される。人間と人間の対立は矛盾ではなく差異であり、差異を感知しうるのは細部をとらえる眼ではなく、人間を総体として理解する理性である。このような意味で、総体としての師に達したのが弟子の完璧さであり、師の存在論的矛盾と弟子の認識の完璧とが結びつくのである。とすれば、弟子の完璧さというのは、始原時代の哲学者が思索しいたような「一」ではなく、複数の師を同時に仰ぐことができる多元性を帯びていると言いうるのではなかろうか。師弟という結合は、その極限において多元性を許容するのであり、このことを三谷隆正という典型的人物は、典型であったがゆえに示唆することができたのだ、と私は思う。
弟子目線で描く「弟子の完璧さ」についてのすばらしい説明。
この本を読んで、広田先生のモデル説のある人物としての岩元禎への興味はむしろ薄れたのだけど、この話は素敵だと思った。
岩元禎がものの見方を志賀直哉にこのように伝授していったのではないかという憶測を、志賀直哉が泳ぐ鯉を観察した文章から追っていくくだり。
クックッと二度ばかり、尾を動かすと、一間位スーッと進む、向こうのタタキで鼻頭を打ちはしまいかと心配していると又クッと尾を一ツ振る、向きが変わつて其ままスーッと進む、実に面白さうだ、
○ for the swiftness and balance of fishes! といふ西洋の詩の句を見たが、魚のバランス、これ位、デリケートによく出来てゐるものは恐らくあるまいと思つた、其運動も亦実に美しいではないか。
岩元禎が古代ギリシアやルネサンス絵画を教えることで志賀直哉に託した夢は、おそらくこのような正確な「視」という形で実現したということができる。たしかに岩元禎は見る人、観照(テオリア)の人であった。あの独断と偏執にもかかわらず、ものを見るときの彼に偏見はなかった。志賀直哉の伝える所では、明治二十四年、教育勅語に礼拝をしなかった内村鑑三の「不敬事件」のとき、一高生徒だった岩元禎はその場に居合わせ眼のあたりに見ていて、それをのちに志賀直哉に語ったという。「岩元さんの話では其時の内村先生の態度は決して不遜な感じのするものではなかつたと云ふ。」このように岩元禎は内村鑑三という人間を見ていた。そして見たものを自分の弟子に語り伝えていた。
夏目漱石の「草枕」に出てくる表現はおそろしく絵画的なのだけど、この時代はこういう教育があったのですね。「ものの観かた」というのは、今もっとも必要な教育だと思う。
教科書で名前を知っているいろいろな人が出てくる。その中心が岩元禎で書かれている当時の学者や哲学者の交流追跡本なのでした。
