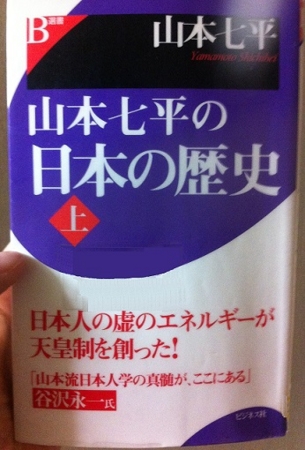
雑誌『諸君!』に22回連載された「ベンダサン氏の日本歴史」が上下巻でまとめられた本。
この本は、日本人の精神性を夏目漱石の「こころ」に登場する人物のセリフ・行動観察から掘り下げ、さらにそのルーツを南北朝時代に北畠親房が残した「神皇正統記」にもとめ、日本の天皇史ごとごっそり根っこから紐解いていくという内容。わたしぜんぜん日本の歴史がわかっていない! と愕然としつつ、夢中で読みました。
なかでも、日本人の「行き方」を、北畠親房の手法説明の後に
まず自己正当化があり、それに基づく過去の再構成があり、その再構成に基づいてまた自己を「正統化」し、それによってその再構成で同時代の再構成を強行しようとする。(209ページ)
とある。戦争の解釈の再構成、他国との関係の再構成。思い当たることばかり。
「日本がひとつになるとき」みたいなキャッチコピーが躍るときの、「あの」精神性、「絆」とかいいだすときの「あの」精神性。あれがどこからやってきたのか。ここではそれが、
虚のエネルギー
として語られます。これに、とにかくうなる。
<115ページ 「去私」=虚のエネルギー より>
『こころ』の非常に面白い点は、漱石が「お嬢さん」の意向という問題を、あらゆる技法を使って封じてしまい、読者に極力、意識させまいとした点にあるであろう。それは、この作品は「お嬢さん」の意向が出てきたら成り立たないからである。(中略)
二人の青年を前において、「お嬢さん」に、何の意向もないとう設定、いわゆる「かりそめの意向」すなわち「もし結婚するなら……」という意向さえないという設定は、「去私の人」という概念の全然ない民族には、いかに漱石の技巧をもってしても、通じないのである。従って、「去私の人」を感覚できない民族、たとえばヨーロッパ人には、この作品は、全く別の作品のように読まれてしまう。それは、この作品の梗概を少し懇切に説明して相手の反応を見れば、だれにでもすぐにわかる。彼らはごく自然に「お嬢さん」は、二人に等分に好意を抱いていると理解する。いわば両方とも好きで甲乙つけがたい心境ということになる。
そうかな? とも思うのだけど、この本全体で「去私」について語られているのを見ていくと、それは梵我一如のような「去私」ではないことが見えてくる。118ページでは、これを「行人」の直にも現われる一面だという。
この「お嬢さん」についての流れから、終戦について、こう語る。
<121ページ 「去私」=虚のエネルギー より>
あの恐るべきエネルギーの根源は何であったかを、いくら探しても見つからない。従って「戦争中の天皇の意向は実はかくかくしかじかであった」などという裏話は、「お嬢さんの意向は、実は『先生』であって、『K』は念頭にはなかった……」などという解説同様、はじめからまったく意味をもたない。
その意向は意味を持たないように書かれているという理由が、この本全体からわかります。とにかくこの解説はうなる。
<125ページ 「先生」=去私を求めた人 より>
「私はまだ復讐しずにいる」と「先生」は言う。一体「先生」の言う復讐とは具体的に何を指すのであろう。おそらくこの言葉には何の具体的内容も計画性もあるまい。これが日本人の「うらむ」という感情であり、従って「彼らが代表している人間というものを、一般に憎む」という言葉はおそらく「彼らが代表している『去私でない』人間を」の意味であり、それは「人をも世をもうらむ」という感情と恐らく同じであろう。
ここだけでもすごいのだけど、その後の展開がベンダサン! このあとの日本人論には背筋が凍る。
<126ページ 「先生」=去私を求めた人 より>
いわゆる「よろしくお願いします」は「あなたを『去私の人』と信じて、一切を委任します」の意味であろうから、これを裏切ることは相手だけでなく「去私」を裏切り同時にその人の「道」を裏切ることになるであろう。この関係を、「人を裏切ることは、律法を裏切ること、すなわち神を裏切ること」というユダヤ教の考え方と対比すると面白いが、これは別の機会に譲ろう。
譲ってほしくなかったけど、このあとの続きがすごいの。
(つづき)
「先生」は「K」を「即道去私」と考え、「お嬢さん」に関しては大丈夫と心底では信じていたことは前述したが、ここで興味深いのは「K」も「先生」を「去私の人」と考えていたことである。「K」がなぜいきなり「先生」に恋を告白したかは、この作品の中の、一番興味深い問題であろう。
そうなんだよなぁ。
<104ページ 「歴史」と『こころ』と「死者の時」より>
「壁」は、前述のように実は、「純粋人間」の逃げ道だから、「壁」をこわすことによって、「壁」のために「純粋」でありえなかったという「生存」のための言いわけを、次々に自らの中でふさいで行く結果になる。その結果は、「K」の如くに自殺するか、一億玉砕という自殺スローガンになるか、「生きていて相すみません」という不思議な「生存の言いわけ」の哲学に生きるか、という状態になる。
これは『「哲学実技」のすすめ』でバッサリやられていた精神性。日本人同士の支配の苦しさは、まさにここにある。
<178ページ 頼朝の「三か条」=「幕府の三原則」より>
頼朝の「三か条」の背後には、当時は、「武家権」はまだ弱く「公家権=朝廷権」も「寺社権」も無視し得ないという実情があったことは言うまでもない。また生涯絶対に楽観せず、自己の子孫についてもおそらく何の希望ももたず、すべての人を絶対に信じなかった「冷徹の人」頼朝の性格も大きく作用しているであろう。しかしこの「三か条」が幕府というものの性格、いわば「純政治的政府」という性格づけを決定したこともまた否定できない。
そしてこの基本的性格をさらに徹底させ、日本人の政治哲学の根本を作りあげたのが北条泰時であった。彼の政治哲学は一言にしていえば、漱石の『こころ』の世界の思考図式と同じ考え方を基にしているのである。
こういうのは、大人になってから歴史の勉強をしないとわからない。この説明は、沁みる。
この本は、聖書・聖典のない国で、日本人の心の中で基準となっているとても曖昧なものの正体「去私」をあぶり出しています。複数の価値観が交錯するとき、日本人たちが切ってきたジョーカー的なカードとしての「去私」。
<233ページ 土地問題とその対策 より>
彼(親房)は、前期天皇制の復活のため「一方万物は悉く国王の物」という原則と、武士的契約を第一と考えた同時代との接点を、「去私」に求めたといえよう。そしてこの観点からすれば、「武士は朝敵なり」であっても、去私の人・泰時の主宰する幕府は合法であり、また後醍醐帝の「文保の御和談」の破棄も合法であった。「去私」は契約の対象となるわけがないからである。
「去私」は契約の対象となるわけがない! と。巧妙だ。
この本は、序盤で「日本人とユダヤ人」「日本人は知らなすぎる 聖書の常識」にある、日本人自身が理解していない日本人性(「赦し」のない世界)を、『こころ』を題材に説明しています。
<34ページ 竹林の薄明と『こころ』より>
「祈り」がないとは「罪」がないことである。「祈り」と「罪」とは、実は同じものなのだが、こういう言い方自体が、おそらく日本では、奇矯な言葉と受けとられるであろう。
だがこの奇矯に受けとられること自体が「忘却」と「赦し」の違いという問題を含む。たとえばイギリス人のような「忘れてはいない、しかし赦す」という言葉は、日本の新聞が完全に誤訳しているように、執念深い、ということではない。「忘れてはいない」ということは、彼らは、自分の状態を語っているにすぎない。現実に「忘れていない」ことを「忘れた」といえば彼らにとっては虚偽であり、相手を欺いているにすぎない。「忘れていない」ことが事実ならば「忘れていない」といわねばならない。そして「忘れていない」が故に「赦し」という言葉がある。
しかし日本には「赦し」という言葉はない。現実には「忘れていない」のに「忘れた」と仮定すること、それが日本人の通常の行き方であり、ここに日本人特有の「時間」がある。
鮮やかすぎる説明。「忘れてあげる」という表現とか、ほんとうに怖い。
日本人って、やっぱりプライド高いよなぁ。責任取らないけど尊重しろ! 契約対象外だけど尊重しろ! みたいな圧がとても多い。
「こころ」を読んだ人は、半分は確実に夢中で読めます。歴史のところは、ちょっとむずかしいかな。わたしはこの本のおかげで、漢文訓読体テキストを読むのが格段に速くなりました。こんなの高校時代ぶりだわ。
(下巻の感想も書きました)
▼わたしは年始から読みはじめていたのですが、今月新装版が出たようです。タイムリィ〜。
