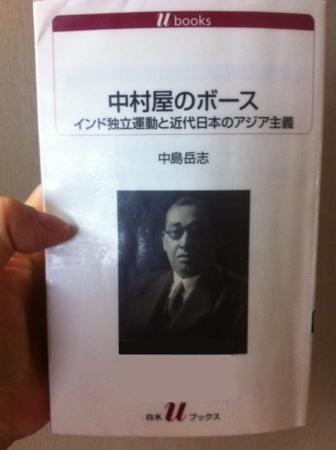
「インドカリーの中村屋」のルーツとなったラース・ビハーリー・ボースの活動が綴られています。大東亜戦争の時代、日本の帝国主義のムードがどんなものであったか、亡命してきたインド人革命家が鮮やかに指摘する言葉の数々に息をのみます。全般、日本人の精神性の課題のあぶり出しかたが神業。正義はかかげてもその奥に思想がなかったり、「敵の敵は味方」という思慮の浅い動機であったり、大切な指摘を感情でスルーしていたり。ドラマチックなストーリーが続くなか決して感傷に浸らず、そのなかに潜む「目的遂行のために思考停止する人間の脆さ」への指摘を忘れない、すばらしい内容です。
このラース・ビハーリー・ボース。単にインドカレーを伝えた料理人などではない。彼は一九一○年代のインドを代表する過激な独立運動の指導者である。(11ページ)
このような紹介から始まります。1912年12月にハーディング総督爆殺未遂事件(ハーディング=イギリスのインド植民地政府の首脳)を起こしたのがボースで、1915年に偽名を使い日本に亡命しています。亡命時にはタゴールの親戚になりすましています。そしてボースが日本へやってきた年に、ガンジーがインドへ帰国しています。
中村屋はもともとパン屋で本郷にあり、「書生パン屋」とも呼ばれていたそうです。それが新宿で中村屋サロンとなり、現在のようなカレーの中村屋になっていきます。この本では「中村屋サロン」の頃も多くのページ数を割いて書かれており、当時の人々の価値観や考え方が上手に切り取られています。
中村屋さんの奥さんである相馬黒光さんは、ボースとグプターという、二人の「追われるインド人革命家」を匿うのですが、そのときに、このような心境だったようです。
どにかくこのインド人を匿ったということは、政府がしないことをこちらがあえてしたのであるから、発覚すれば問題は大きい。われわれは何らかの処置に服さねばならないだろう。その時は当の責任者として私が出よう。なぜといって、二人を匿う部屋のこと、食事のこと、その他いっさい身辺をわきいまえるのは主婦なのだから、それに私が囚えられて家にいなくても、子供たちを世話してくれる人はあるし、商売は本郷以来私の名義のままで、それはちょうど私が勝手な振る舞いをできるという証拠にもなる。相馬は「どうも家内が出過ぎたことをして」そう言っていればすむ。そうすれば商売にも影響はない。
(131ページ「二人のインド人の中村屋生活」より)
アツいです。そして三ヶ月半の共同生活で絆と連帯感が生まれた後、ボースが中村屋を出て行く日に黒光さんは涙を流します。その別れの日の描写に
ボースは自動車に乗ろうとしてこちらを見上げた。羽織袴がよく似合って堂々として、立派な日本紳士であった。
と残されているのですが、そこについての著者さんの指摘が鋭い。
ここでは、黒光が和服のボースに「立派な日本紳士」の姿を見ていることに注目する必要がある。中村屋関係者や玄洋社メンバーは、しばしばR・B・ボースの姿や態度を「日本人以上に日本的」だと評し、そのような側面を高く讃えている。彼らの外国人に対する評価基準が「日本的であること」に置かれている点には、やはり大きな問題が付きまとう。R・B・ボースのような異文化への順応能力に秀でた人物にとって、このような姿勢は友好関係を強固なものにする方向に作用した一方で、グプターのような、時に従順ではないアジア人は、「日本的礼節を重んじない人物」として冷遇されることが往々にして見られた。このようなアジア人を「日本的か否か」で評価するあり方は、のちに中国や東南アジアに対する植民地支配を推し進める過程で、大きな問題を引き起こすことになる。
(145ページ「新宿中村屋を出る」より)
この指摘が当時「日本的な」忠義や礼節を重んじ、それをアジア他国にも求め、中国・朝鮮からの反発や抵抗、無理解無関心に出くわすたびに苛立ちを感じる日本の国家主義団体につながるとするのは少し強引な気もしますが、でもわたしは共感します。
玄洋社・黒龍会のメンバーにとって、R・B・ボースの政治的・思想的発言は、一貫して重要なものではなかった。また、彼が語るインドの歴史過程や過酷な現状についても、その詳細については、ほとんど関心が向けられなかった。彼らにとって重要だったのは、イギリスの植民地支配によって悲惨な状況におかれているインドの革命家が、日本に期待をかけていることによって自尊心が満たされることであり、その人物を自分たちが劇的な形で保護したという美談によって、自らのアジア主義的行動が、意義あるものとして正当化されることであった。
R・B・ボースは、確かに玄洋社のメンバーによって助けられた。しかし、彼の思想や主張の多くの部分は、皮肉なことに、彼を窮地から救った心躍る義勇談によって、常に脇へと追いやられたのである。
(153ページ「玄洋社・黒龍会のアジア主義とR・B・ボース」より)
ボースさんは元来、どんな信念を持った人だったのでしょう。
ボースさんは、日本に馴染んでいくにつれ主張のニュアンスを変えていきますが、いつも半分は冷静に日本のことを見ている人でした。
R・B・ボースは、イギリスの植民地支配からインドを独立させアジア主義の理想を実現させるためには、日本という帝国主義国家の軍事力に依存せざるを得ないという逆説を主体的に引き受けた。(387ページ)
という人であるのだけど、背景がその直前に書かれており、
それは
彼はインドの宗教哲学者オーロビンド・ゴーシュの思想に大きな影響を受けており、究極的には国民国家体制を超えた世界のあり方を志向していた。そして、それを実現するため、東洋精神の発露としてのアジア主義を唱えた。(386ページ)
というもの。
最後の一行は「なんでそうなる?」という感じもします。
この点について著者さんは
彼の西洋認識は、非常に単一的でステレオタイプ化されたものであり、西洋における思想体系やその宗教・文化の多様性を捉えようとする視点が著しく欠如している。(195ページ)
と指摘しつつ、一方で
彼は本格的な哲学者や思想家ではないため、その記述は断片的で、体系的なものでは決してない。また、特筆すべき斬新な議論や緻密な哲学的理論を展開したわけでもなく、思想そのものとしては粗が多い。しかし、R・B・ボースは独学でさまざまな分野の書物を読み、幅広い知識を身につけつつ、自己の抱いている思想信条を率直に表現してきた。彼のような高等教育を受けていない非エリートのインド人革命家が、当時の日本において如何なる思想を巡らし格闘していたのかを知ることは、「二○世紀アジア」という時空間を考察する上でも重要であろう。(259ページ)
とも語ります。
この視点がこの本の大動脈。
この本の序盤で、ボースさんについてこのような説明があります。
R・B・ボースは、次第にオーロビンドの宗教哲学に深く影響されていった。そして、彼はヒンドゥーの聖典である『バガバット・ギーター』を読み、そこで説かれた「自己犠牲の精神」(Atmasamarpana.アートマサマルパーナ)に激しく心を動かされた。彼はオーロビンドを通じて宗教哲学の重要性と普遍性を深く認識し、これ以降、自己の欲求を棄てて独立運動に邁進することを『バガバット・ギーター』の精神に依拠するものと捉えるようになった。(34ページ)
この「自己犠牲の精神」は、ボースさんのなかでは「他のために己を犠牲にする家族主義」を理想とし、「個人主義は己のために他を犠牲にするもの」という構図になっていました。この本は日本の帝国主義的マインドとボースさんの目的の結びつきを中心に書かれていますが、アツくなるときの点火のしかたがそもそも好相性であったように見えます。
ボースさんは、冷静でもありました。
日本は配合の悪い洋装を為す事を以って白人と同一に冷遇されようとしたのである。(193ページ)
容赦ない指摘です。
この時代は壮絶で、そんなボースさんも死期が近づくとアプローチが変わってきます。
一九三○年代後半以降のR・B・ボースは、インド独立の実現を最優先するプラグマティストとして日本の帝国主義的動きを追認し、日本による「アジア解放」戦争を推し進めるための言説を繰り返した。さらに、イタリア・ドイツのファシズム体制を容認し、その両国と日本の連帯によるインド解放を目指した。
(297ページ「イタリア・ドイツとの連携」より)
なんと、こうなる。
「目的遂行のためなら意志をこう表現する」「相手をこう批判する」ということを主体的に行ってきたボースさんの行動、それをとりまく日本人たちの精神あり方にハッとさせられるやり取りが多く、久しぶりにズシーンと来ました。「信じること」の強さと脆さの切り取り方が秀逸です。
インド思想と日本の精神は、ブレンドによってはこうなってしまうという側面も見せつけられ、いろいろと身の引き締まる気分で読みました。とても重要な指摘と示唆に富んだ一冊です。主体的に考えるor考えようとする人に、はげしくおすすめです。
